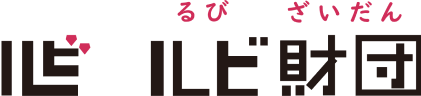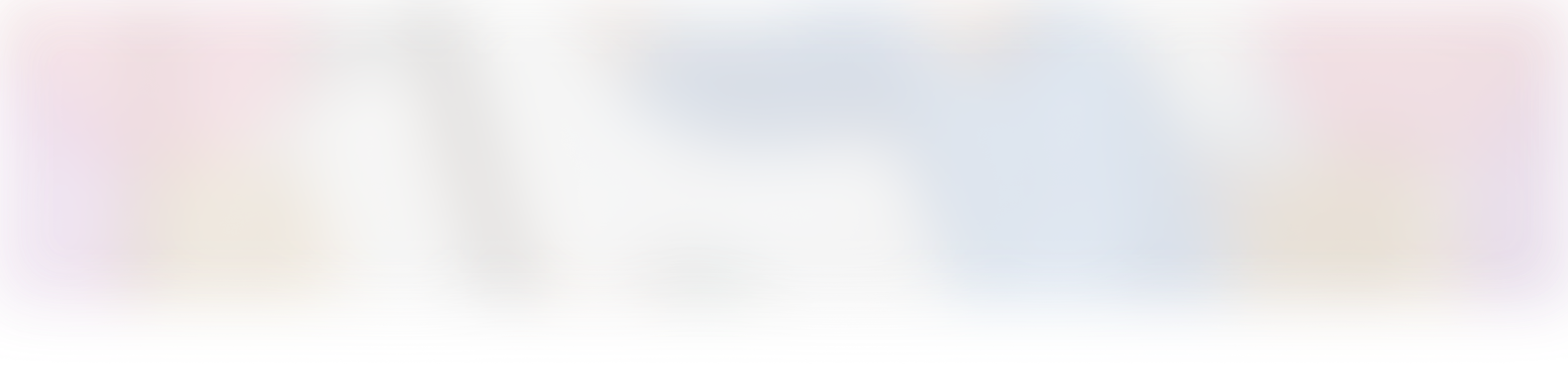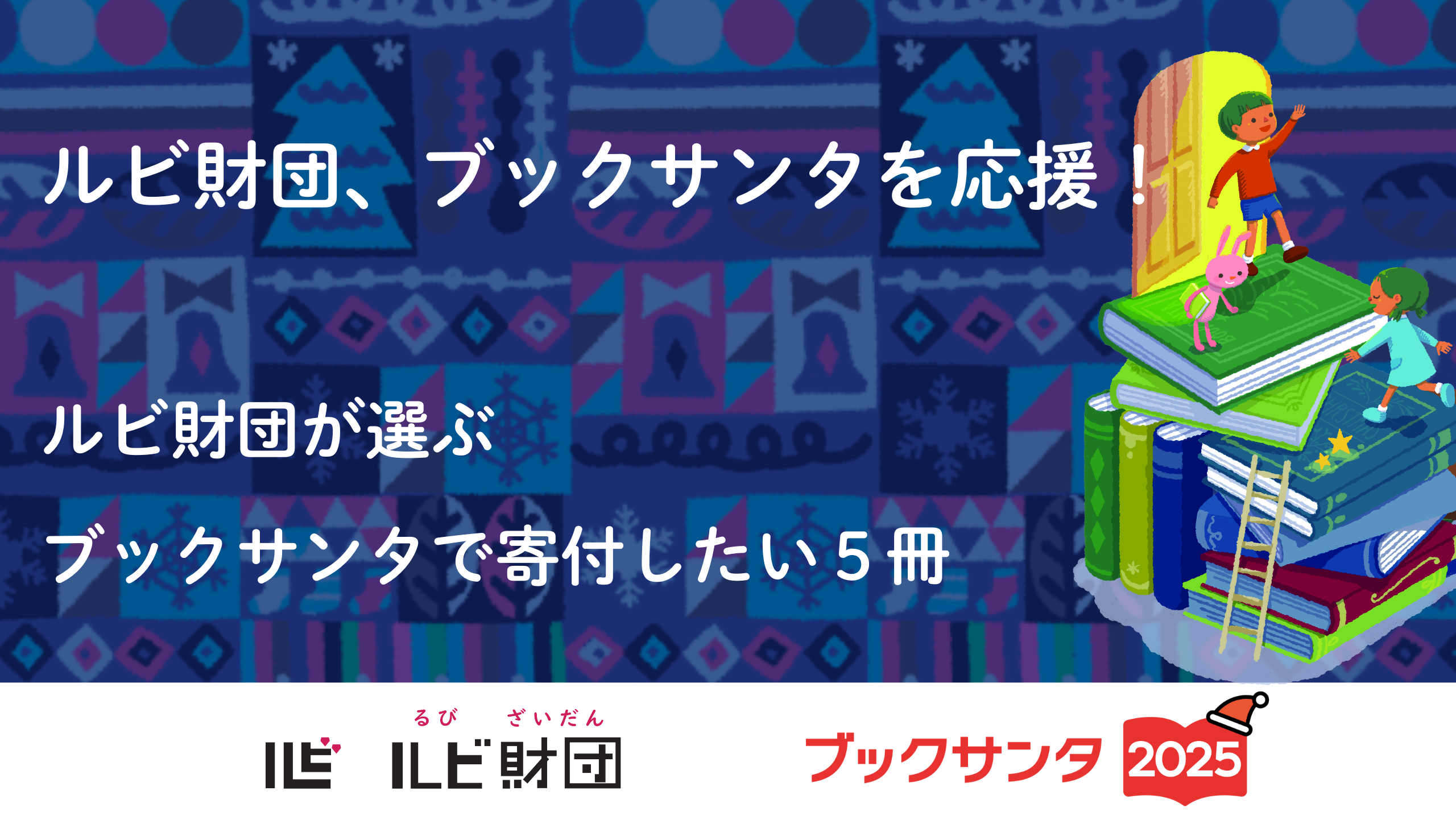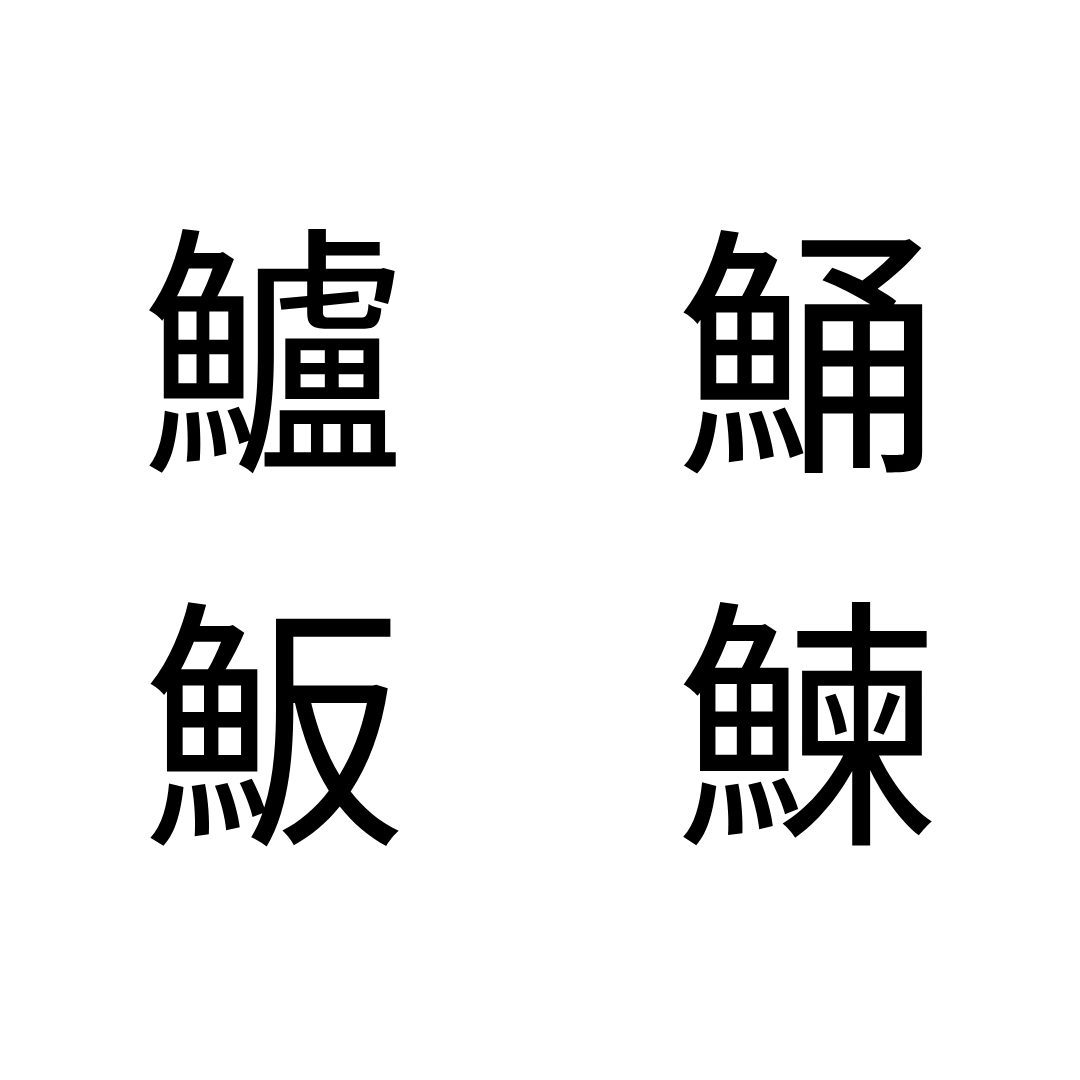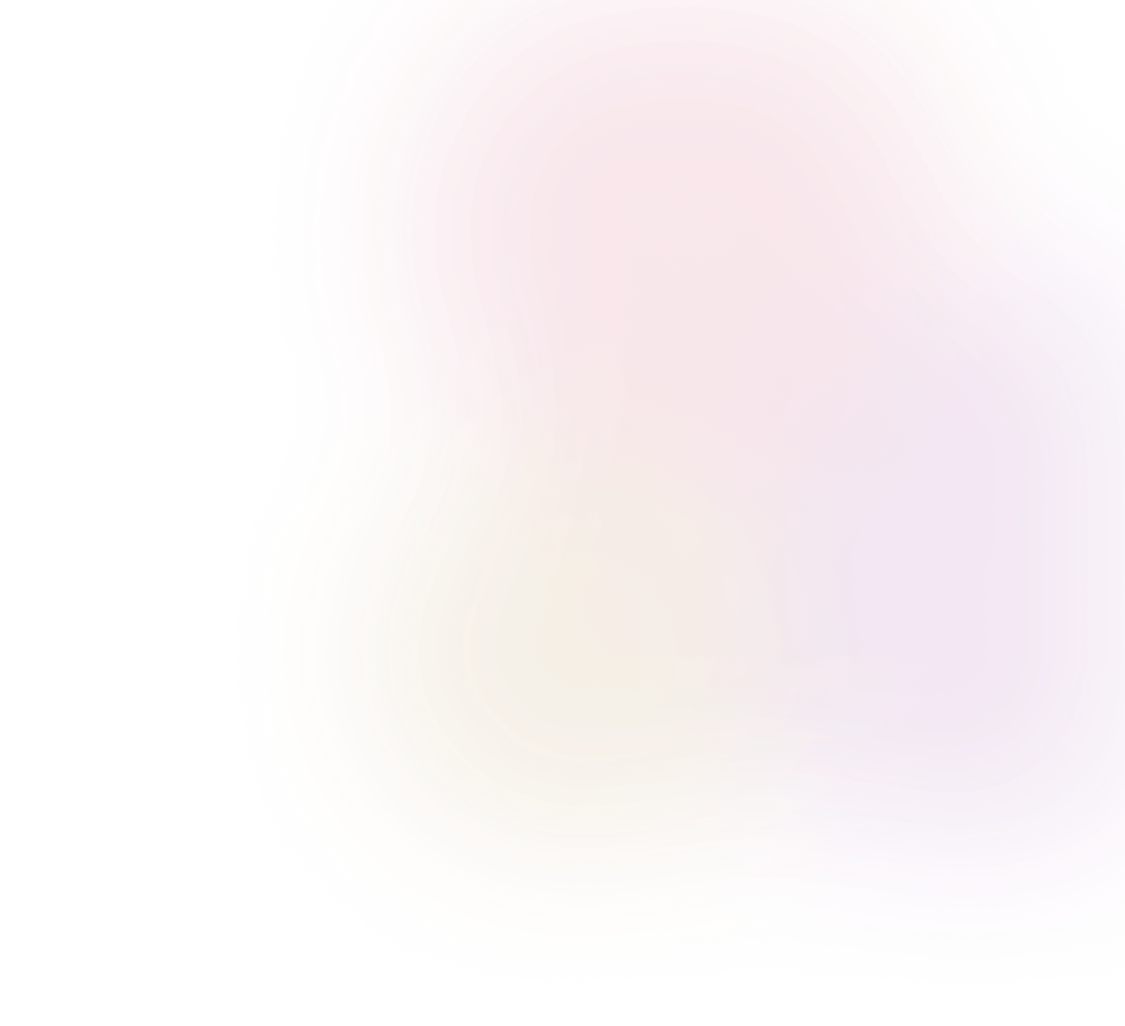
読者の幅を広げる、読みやすさに配慮した本づくり/児童書作家・江口絵理さん、児童図書出版社「さ・え・ら書房」・佐藤洋司さん
インタビュー
2025/09/30


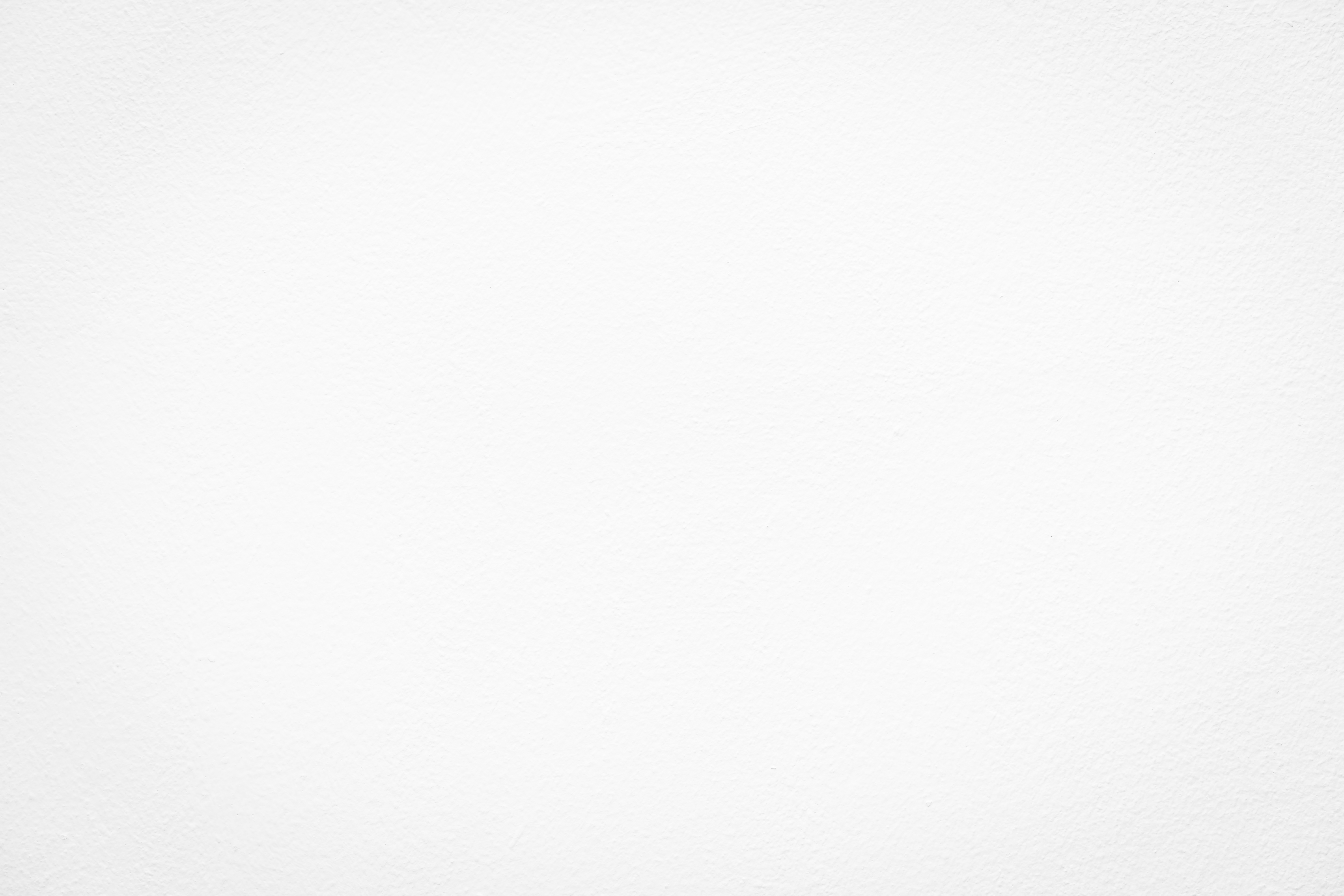
動物や自然、人物に関する本の執筆を手がける江口絵理さん。“いきざま”に関心があるという江口さんの執筆対象は、動物から人物まで幅広いのだそうです。
また、児童を対象とした著書も多いので、江口さんが手がける本にはルビが多い印象があります。中でも、『アフリカで、バッグの会社はじめました――“寄り道多め”仲本千津の進んできた道』には本文中に多くルビが振ってあったので、丸善丸の内店で行われた「ルビフル本選書」プロジェクト*にて選書させていただきました。
今回は、江口絵理さんと「さ・え・ら書房(児童図書出版社)」代表取締役社長で『アフリカで、バッグの会社はじめました』担当編集者でもある佐藤洋司さんのお二人にお話を伺いました。
*一般向けの本の中でもルビが多めにある本や大人が読んでも面白く親子で楽しめる児童書などのルビが多い本を選書するプロジェクト。
大切なのは敷居を下げる配慮
江口さん:
私が本をつくるときは、子どもが読むと面白いというだけではなくて、大人も面白いと思える本を目指しています。基本的には「子どもの本」を書いているんですけど、子ども相手だからといって子どもっぽい言葉で語りかけるのではなく、今の私の年齢なりの言葉で語りかけたい。つまり、相手が誰であれ人間同士として話をしたいといつも思っています。嬉しいことに実際、書籍のレビューやSNSを見る限りでは結構大人の方も読んでくれているようです。『アフリカで、バッグの会社はじめました』は課題図書(中学校の部)になったので「娘が読んでいたのですが、私も読みました」というような感じで親御さんが感想を書いているのをよく見かけます。これは本当に私の理想としていた拡がり方ですね。この本は将来のキャリアパスや進路について悩み始める子どもを意識して書いたので、中学生以上を対象に書いたものではあるのですが、その1~2学年下の子どもたちにももちろん読んでほしいと思っていました。本って、少し背伸びして読む子が必ずいますし、逆に、本が苦手な子でも1~2学年下くらいまでの漢字をカバーできていれば、なんとか読み進めることができると思うんですよね。自分自身のことを思い出してみても、苦手な科目だとその学年で習ったことを完璧に覚えるのは難しいじゃないですか。だから作り手が少し下の学年の漢字までカバーして、より多くの人が難なく読めるように努力することは大事なことだと思いますね。
江口さん:
『クジラがしんだら』(童心社、2024年)は絵本なんですけど、この本は“科学を絵本で”というコンセプトなので、深海生物や新しい科学に興味がある大人にもぜひ読んでほしいと思って書きました。なので、子どもっぽくなりすぎないように気をつけましたね。とはいえ、絵本なので本文中に「鯨骨生物群集」などの専門用語はあえて使わないようにしたのですが、子どもの好奇心って果てしないので、もしかすると難しい言葉にかえって惹かれて「こういう言葉を覚えられたことが嬉しい」と感じるかもしれませんよね。でもどちらにせよ読めなかったら覚えようがないことなので、そういう意味でも子どもにとって、ルビがあって読むことができるというのは大事なことだと思います。子どもたちが初めて漢字に出会うのは「絵本」だと言われていますから、全部ひらがなで表記するのではなく、例えば「“海”ってこういう字なんだな」というのを漢字とルビを読みながら自力で統合できるようになればいいなと思っています。
私たちルビ財団としても、大人も子どもも楽しめる本が世の中にもっと増えればいいなと考え「ルビフル本選書」プロジェクトを行っています。特に「大人=漢字が読める」と考えられがちですが、実際の世の中には外国ルーツの方やディスレクシア(読み書きが困難な学習障害の一種)の方で、漢字を読むのが困難な方々も多くいらっしゃいます。ルビは、漢字が読めない子どもはもちろん、大人にとってもユニバーサルデザインであり多様性を大事にする社会において今後益々重要な配慮となり得るはずです。
江口さん:
大人の方にとってルビがどれほど大事であるかということについては、そこまで真剣に考えてこなかったので、「ルビフル本」に選んでいただき、ルビ財団のHPを拝見したことで初めて重要性を知ることができました。私はどんな本でも最初の入口はむやみに高くせず「どうぞ入ってきてね」という方がいいと思っています。本を進んで読む人がどんどん少なくなってきている今の時代だからこそ、作り手がそういった配慮をするのは益々大事なことですよね。なので、これから他の本を書く上でもルビを大事にしようと改めて思いました。
“読んでもらう”ために。わかりやすさを優先したルビの振り方
これまであらゆる出版業界の方々にインタビューする中で「ルビの振り方に(明確な)ルールはない」ということがわかってきています。児童書の出版社である「さ・え・ら書房」での判断基準はどのようになっているのか、編集者の佐藤洋司さんのご意見を伺いました。
佐藤さん:
弊社では、「この作品は小学校何年生から習う漢字にルビを振ろう」と決めて、ソフトを使ってルビを振っています。でも、そのソフトを使っても(文脈によって変化する)読み方を間違えるので、結局は人の目でチェックをしますね。他にも、読みにくいと感じる漢字には、習う学年に関係なく任意でルビを振るので、最終的にはやはり個人の主観でルビを振る判断をしていますね。私の場合は、パラグラフか章単位で初出の人名や固有名詞にはルビを振るように気をつけています。ルビが多いと“うるさい”と感じる方もいらっしゃるみたいですけど、なるべくケチらないようにしていますね。これは個人的な見解ですが、多少字面がうるさくなったとしても「読めないよりかはいいかな」と思っているので。でもこれは私の場合なので、他社や他の編集者がどのようにルビを振っているのかはよく知らないですね。考えてみると、著者を介して“他所の雰囲気”を知るぐらいで、ルビの振り方について情報交換したことはないんですよ。なので今回ルビ財団さんのお話を聞いて、ルビが外国ルーツの方や識字障害がある方にとっても助かるものだと知り、今後の参考にしようと思いました。
江口さん:
一般書、特にビジネス書の編集部では効率的にたくさんの本を作って出すことが求められるので、ルビ入れの方針をじっくり考える時間は作りにくいかもしれません。対して、児童書は1冊1冊かなりの時間をかけて編集者が向き合うので、ルビに関しても立ち止まってその本ごとに方針を決めているケースがほとんどだと思います。とはいえ、重要なのは一般書か児童書かではなく、作り手に、“この人に届けたい”という読み手の顔が浮かんでいるかどうかではないでしょうか。読み手を“読者一般”と想定していると、ルビの優先順位は下がってしまうと思うんですけど、届けたい相手がはっきりしていると「この人には読めるだろうか?」という意識が働きますよね。たしかに、客観的に見ればルビ入れは「手間」なんですが、昔、私がルビに限らずすごく手間をかけてつくった本を、凄腕の先輩編集者さんが「作り手が苦労した分、読み手の苦労を減らしてる」と評価してくださって、とても報われたような気がしたんです。手間をかけることは、読み手に届けたいという気持ちそのものなんだな、と。一方で、ルビを増やさない理由は特になくて、「漢字が読めないことの不便」がたまたま作り手から見えていなかっただけという現場もあると思います。だから、ルビ財団さんが「ルビって大人にとっても、誰にとっても大事だよ」と発信されていることは、なんとなくルビの順位を下げていた作り手が「ルビのおかげで助かる人がいるんだ」という気づくきっかけになる大事なことだなと、今日お話していて感じました。